あなたを夢中にさせた素敵な推理小説の書評を募集しています。
お気に入りの推理小説を200〜800字で紹介してください。
当書房編集部で選考の上、当コーナーにて紹介させて頂きます。
送り先はコチラ
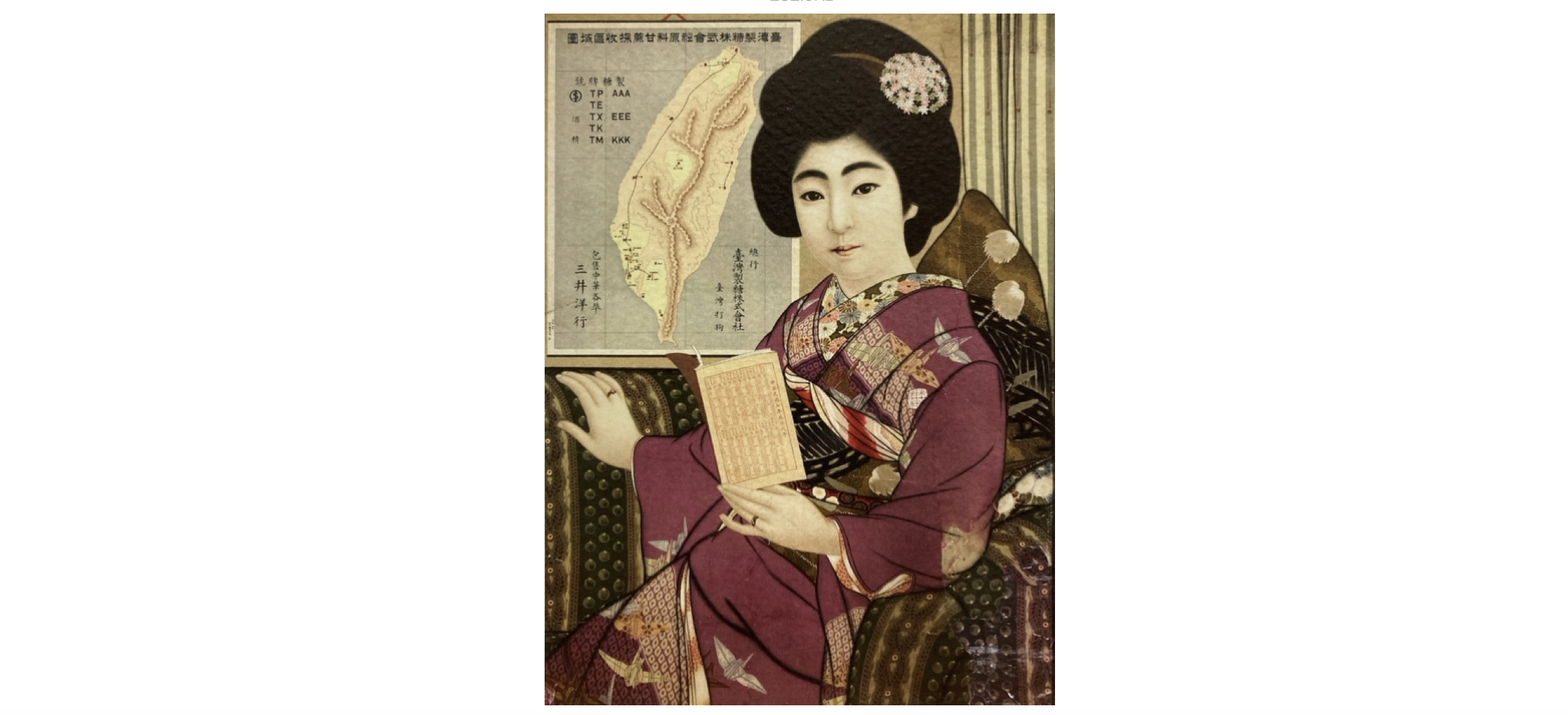 人間は推理する葦である
人間は推理する葦である 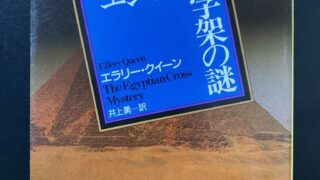 人間は推理する葦である
人間は推理する葦である  人間は推理する葦である
人間は推理する葦である 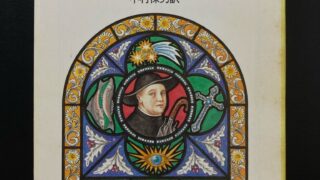 人間は推理する葦である
人間は推理する葦である  人間は推理する葦である
人間は推理する葦である  人間は推理する葦である
人間は推理する葦である  人間は推理する葦である
人間は推理する葦である 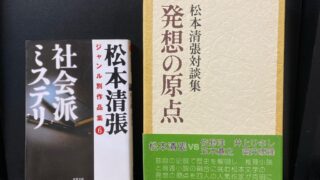 人間は推理する葦である
人間は推理する葦である 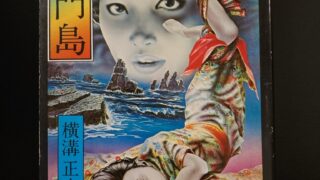 人間は推理する葦である
人間は推理する葦である 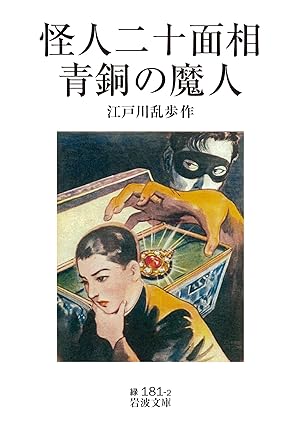 人間は推理する葦である
人間は推理する葦である 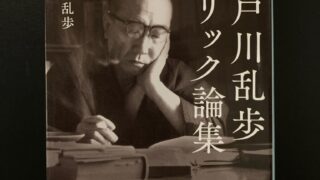 人間は推理する葦である
人間は推理する葦である